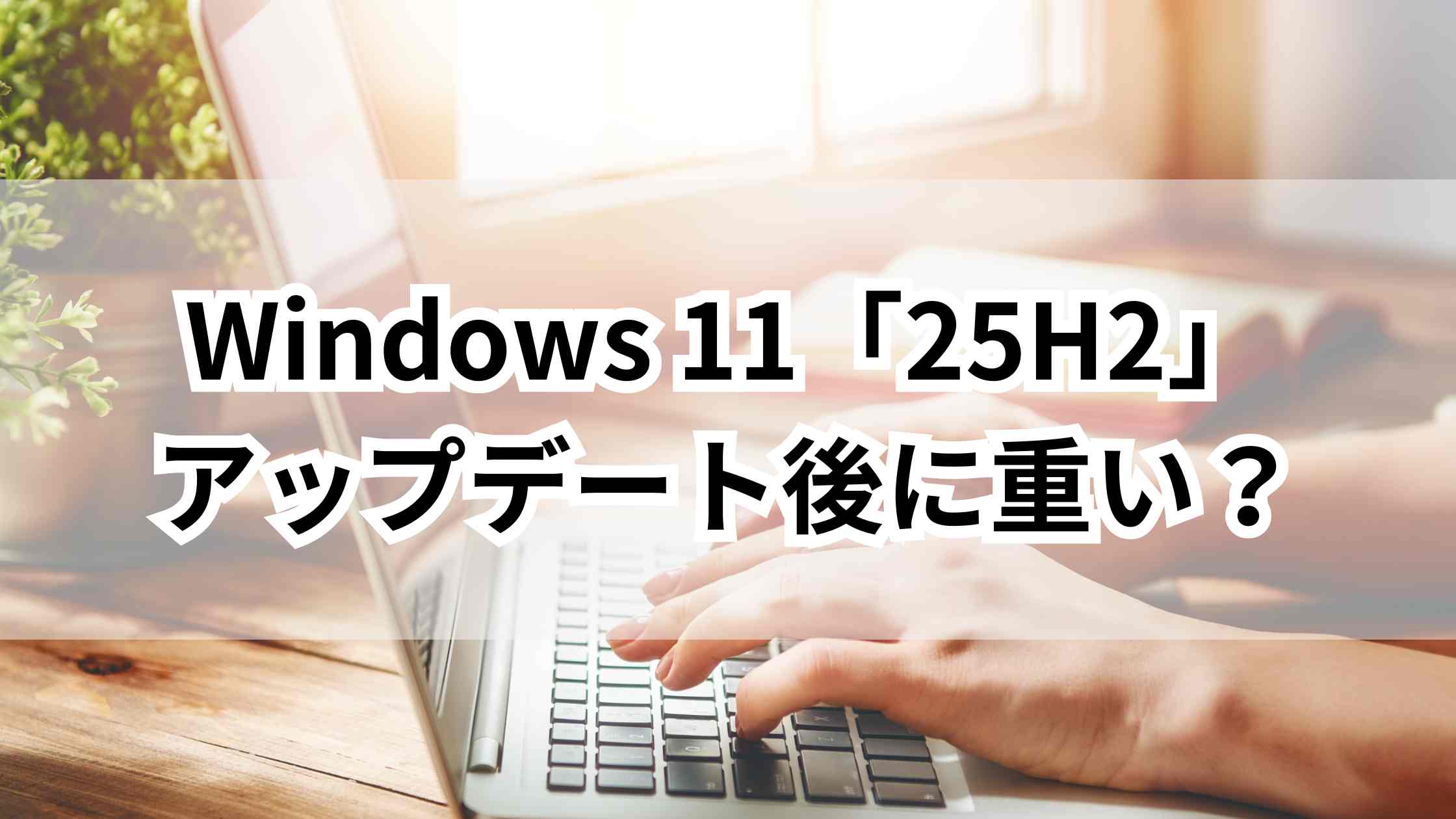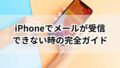Windows 11を「25H2」に更新したあと、「なんだか動作が重い」と感じていませんか。
実は25H2自体は軽量な“有効化パッケージ型アップデート”で、基本性能は24H2と同等です。
つまり、恒常的な性能低下はほとんどの場合ありません。
ただし、更新直後にはバックグラウンドで検索インデックスの再構築やOneDriveの同期、Defenderスキャンなどが動作し、一時的にCPUやディスク負荷が高まります。
この記事では、そうした「一時的な重さ」の原因をデータで見極める方法と、誰でもできる具体的な改善ステップを紹介します。
「アップデートで重くなった?」と感じたときに役立つ、信頼性モニター・イベントビューアーを活用した“測って直す”実践ガイドです。
Windows 11「25H2」が重く感じるのは本当?まずは結論から
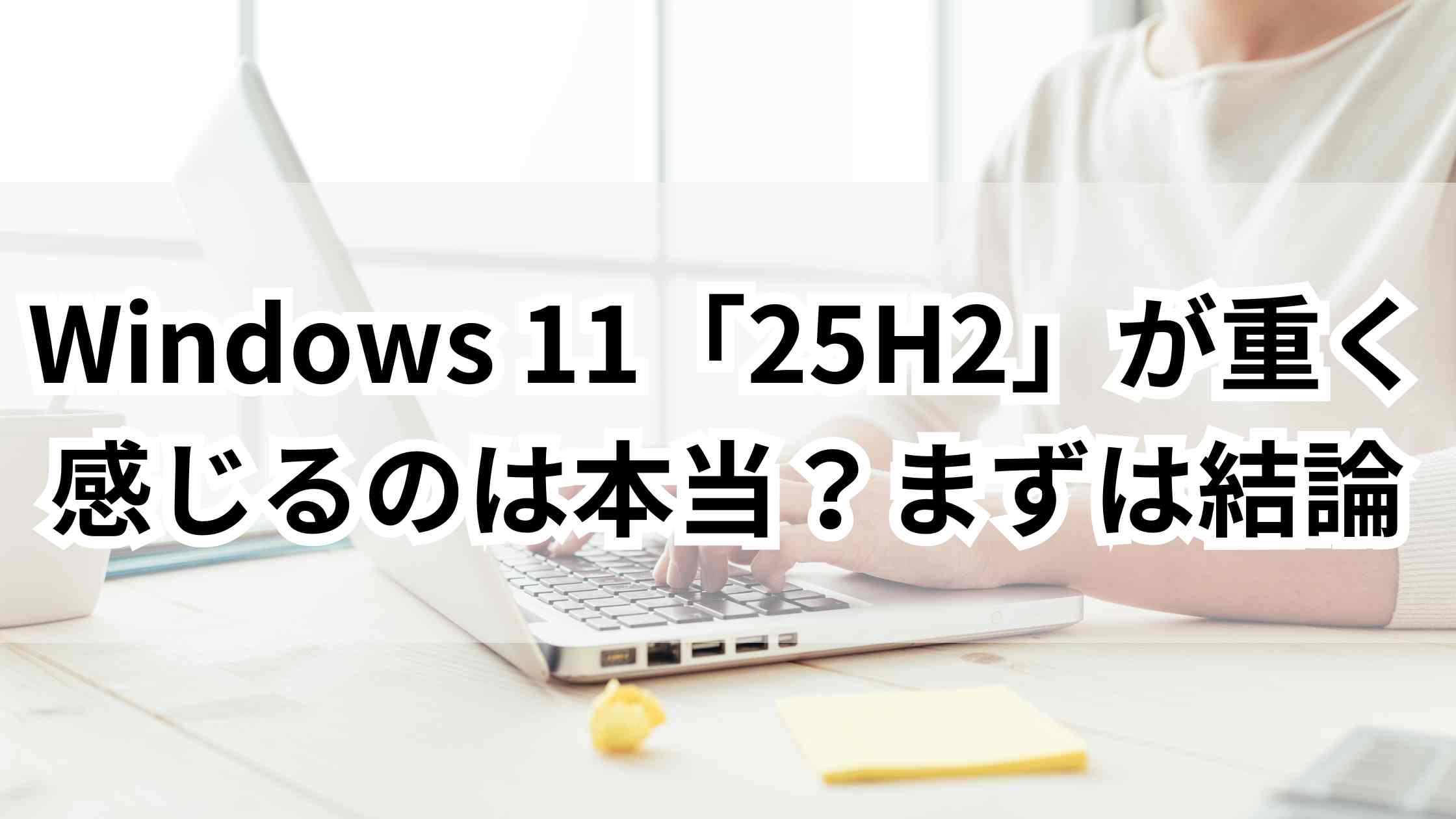
Windows 11の最新バージョン「25H2」へアップデートしたあと、「動作が重くなった」と感じる人が増えています。
ですが25H2は基本的に24H2と同等性能の小規模アップデートであり、設計上、恒常的に動作が遅くなることは想定されていません。
体感的な“重さ”の多くは、アップデート直後に走るバックグラウンド作業(検索インデックスの再構築やDefenderのスキャン、OneDriveの再同期など)が原因です。
これらは数時間〜数回の再起動で落ち着くため、焦らず様子を見るのが第一歩です。
25H2は小規模アップデート、基本性能は24H2と同等
Windows 11の「25H2」は、前バージョン24H2に“有効化パッケージ”を追加する方式で配信されています。
これはシステム全体を入れ替える大型アップデートではなく、既存の環境を維持したまま差分的に機能を有効化する設計です。
そのためOSコアやドライバ構造に大きな変更がない=性能低下のリスクが小さいのが特徴です。
Microsoft公式情報でも、25H2のビルド(26200系)は安定性を重視した構成であると明記されています。
| 項目 | 24H2 | 25H2 |
|---|---|---|
| 更新方式 | 大型更新(OSコア更新あり) | 有効化パッケージ(差分的更新) |
| 対象ビルド | 26100系 | 26200系 |
| 主な特徴 | AI機能・セキュリティ拡張 | 安定性維持・修正中心 |
更新直後に重く感じる“あるある”の正体とは
更新後の“重さ”の正体は、バックグラウンドで進行する再構築・同期・スキャンといった一時的な負荷です。
検索インデックスの再生成やMicrosoft Defenderの初回スキャンは、CPUやディスクI/Oを大きく使うため、短時間だけ体感速度が下がります。
また、OneDriveやMicrosoft Storeアプリの同期・最適化も同時に動くため、特にSSDやネットワークが遅い環境では顕著に感じられます。
つまり、更新直後の“もっさり感”は不具合ではなく、正常な安定化プロセスの一部というわけです。
| 現象 | 主な原因 | 解消までの目安 |
|---|---|---|
| 起動が遅い | ドライバ再最適化 | 数回の再起動 |
| ファイル検索が遅い | インデックス再構築 | 1〜2時間 |
| ディスク使用率が高い | OneDrive同期 | 同期完了後に収束 |
25H2アップデートの中身と設計思想を理解しよう
25H2のアップデートは“機能拡張”というより“安定性と保守性の強化”を目的としたものです。
ここでは、内部構造やMicrosoftが採用している有効化パッケージ方式の背景を理解し、なぜパフォーマンスが維持されるのかを整理していきましょう。
有効化パッケージ方式とは?24H2との違いを整理
「有効化パッケージ(enablement package)」とは、既にOS内部に用意された機能を“スイッチON”するだけの軽量な更新方式のことです。
この方式では、従来のように数GB単位でシステムファイルを置き換える必要がなく、更新によるCPU・メモリ負荷が大幅に軽減されます。
更新時間の短縮と安定動作を両立できる点が最大の利点です。
| 比較項目 | 従来の大型更新 | 有効化パッケージ |
|---|---|---|
| 処理内容 | OSコア入れ替え | 既存機能の有効化 |
| 更新サイズ | 数GB | 数百MB程度 |
| 再起動回数 | 複数回 | 1回のみ |
Microsoft公式が示す「25H2の安定性重視方針」
Microsoftは25H2を“新機能の拡張よりも安定性と保守性を優先したアップデート”と位置付けています。
例えば、古いコンポーネント(PowerShell 2.0やWMIC)の削除、回復環境(WinRE)の修正など、裏方の信頼性を高める施策が中心です。
特に2025年10月に報告されたUSB入力不能問題(WinRE)はKB5070773で修正済みであり、累積更新を適用することで安全性が確保されます。
このように、25H2は派手さこそありませんが、日常的な安定性を支える重要なアップデートといえます。
| 改善領域 | 概要 |
|---|---|
| セキュリティ | 回復環境の脆弱性修正(KB5070773) |
| 保守性 | 古い管理ツールの削除、コード整理 |
| 信頼性 | Defender・OneDriveの安定動作向上 |
“重くなった”と感じる原因を徹底解剖
Windows 11の25H2アップデート後に「操作が遅い」「動作がもっさりする」と感じる場合、ほとんどが一時的な負荷要因によるものです。
ここでは、更新直後に発生しやすい具体的な原因を整理し、それぞれどのように見分け、どのくらいで解消されるのかを解説します。
検索インデックス再構築・Defenderスキャンによる一時的負荷
更新後にWindows Searchサービスが動作し、ファイルやアプリのインデックスを再構築します。
これは検索を高速化するための重要な処理ですが、CPUやディスクI/Oを長時間占有することがあります。
また、Microsoft Defenderが初回のフルスキャンを実行することもあり、同時に走ると一時的に操作が重くなる原因となります。
時間を置くことで自動的に収束しますが、手動で「クイックスキャン」モードに変更するのも有効です。
| 原因 | 影響範囲 | 解消までの目安 |
|---|---|---|
| 検索インデックス再構築 | CPU・ディスク | 1〜2時間 |
| Defenderフルスキャン | CPU・メモリ | 30分〜数時間 |
ドライバやアプリの再最適化が必要なケース
アップデートによりドライバ構成が部分的にリセットされることがあります。
特にグラフィックス・SSD・チップセットドライバが古い場合、起動や描画処理が遅くなることがあります。
ベンダー提供の最新ドライバを適用することで劇的に改善するケースも多いです。
| デバイス | 症状 | 対処法 |
|---|---|---|
| GPU(NVIDIA/AMD/Intel) | ウィンドウ描画が遅い | 公式ユーティリティで更新 |
| SSD | 起動・読み込みが遅い | メーカー製ツールでファーム更新 |
| チップセット | 全体的に鈍い | マザーボード製品サイトで更新 |
OneDriveやストアアプリの再同期によるディスク負荷
OneDriveは更新直後にファイルの整合性チェックを行います。
大量のファイルを同期している場合、ネットワーク帯域やディスクI/Oが圧迫されます。
また、Microsoft Storeアプリの自動更新も同時期に動作するため、複合的に“重い”と感じやすい状況です。
同期が完了すれば動作は自然に安定します。
| 要因 | 影響 | 解決の目安 |
|---|---|---|
| OneDrive再同期 | ネットワーク・ディスクI/O | 数時間〜1日 |
| Microsoft Store更新 | CPU・ディスク | 自動で完了(数十分) |
本当に遅くなった?客観的に検証する3つの方法
「重くなった」と感じたとき、感覚ではなくデータで確認することが重要です。
Windowsには、動作の遅延やエラーを客観的に計測できる標準ツールが複数用意されています。
ここでは代表的な3つの方法を紹介します。
イベントビューアーで起動時間を数値化
イベントビューアーを使うと、PCの起動にかかった時間や遅延原因を確認できます。
「イベントビューアー」→「Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance/Operational」を開き、Event ID 100(起動時間)を参照します。
更新前後のブート時間を比較することで、実際に遅くなったのかを数値で判断可能です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Event ID 100 | 起動全体の所要時間 |
| Event ID 101〜103 | 遅延を引き起こすプロセスの特定 |
信頼性モニターで更新後のエラーを把握
「perfmon /rel」と入力して信頼性モニターを起動すると、システムの安定性履歴がグラフで表示されます。
アップデート直後にエラーや警告が集中している場合は、特定のアプリやドライバが原因の可能性が高いです。
グラフをクリックすれば詳細情報が表示され、エラー発生アプリを直接確認できます。
| 指標 | 見方 | 対処の方向性 |
|---|---|---|
| 安定性スコア | 10に近いほど安定 | 低下時はアプリの再インストール |
| エラー発生日 | 更新直後に集中していれば一時的負荷 | 継続時は原因調査が必要 |
WPR/WPAでCPU・I/Oのボトルネックを特定
上級者向けですが、Windows Performance Recorder(WPR)とAnalyzer(WPA)を使うと、システムの詳細トレースを取得できます。
これにより、どのプロセスがCPU・メモリ・I/Oを圧迫しているのかを正確に特定できます。
「重い原因が見えない」ときの最終手段として非常に有効です。
| ツール | 用途 | 入手先 |
|---|---|---|
| WPR/WPA | 詳細パフォーマンス解析 | Windows ADKに同梱 |
| Event Log Explorer | 起動イベントの可視化 | 公式サイトから入手可能 |
実用的な対処法と改善ステップ
「重くなった」と感じたときに最も大切なのは、やみくもに設定をいじらず、順序立てて確認・対処することです。
ここでは、短時間で実行でき、かつ効果が高い順に整理した実践チェックリストを紹介します。
累積更新・再起動・放置で安定化を待つ
まず最初に確認すべきは、最新の累積更新プログラムが適用されているかどうかです。
設定 → Windows Update → 更新の確認でKB5070773以降がインストールされているかを確認しましょう。
更新適用後は、PCを2〜3回再起動し、AC電源接続のまま20〜30分程度アイドル状態で放置するのがポイントです。
この間にバックグラウンドでインデックス再構築や同期処理が完了し、動作が安定します。
| 手順 | 目的 | 所要時間 |
|---|---|---|
| 累積更新の適用 | 最新修正の反映 | 10〜20分 |
| 再起動を複数回実施 | キャッシュ再初期化 | 5〜10分 |
| アイドル放置 | バックグラウンド処理の完了 | 20〜30分 |
スタートアップやインデックス設定を見直す
タスクマネージャーの[スタートアップアプリ]タブを開き、影響が「高」と表示されているアプリを一時的に無効化しましょう。
不要な常駐アプリを減らすことで、ログイン直後の負荷を大幅に下げられます。
また、「設定 → プライバシーとセキュリティ → 検索」でインデックスの対象範囲を見直すのも効果的です。
業務フォルダや写真など、検索対象にする必要のない場所を外すことで、検索再構築の負荷を軽減できます。
| 設定項目 | 推奨操作 | 効果 |
|---|---|---|
| スタートアップアプリ | 影響「高」をオフ | 起動時間短縮 |
| 検索インデックス | 対象フォルダを限定 | ディスク負荷軽減 |
| バックグラウンドアプリ | 不要なアプリを停止 | メモリ使用量削減 |
ドライバ・Defender設定・イベントログで根本対策
安定化を図る上で見落とされがちなのがドライバとセキュリティ設定の最適化です。
GPU・チップセット・SSDのドライバは、ベンダー公式のユーティリティ(GeForce Experience、AMD Adrenalin、Intel Driver & Supportなど)から更新しましょう。
また、Defenderの設定を「クイックスキャン中心」「アイドル時のみ実行」に変更すると、使用中の負荷を抑えられます。
最後に、イベントビューアーでEvent ID 100〜103を確認し、起動遅延を引き起こしているアプリを特定・整理します。
“感覚的に重い”から“数値的に軽くした”へ切り替えることが重要です。
| 対象 | 具体的な操作 | 目的 |
|---|---|---|
| GPU・SSDドライバ | 最新バージョンへ更新 | 描画・起動速度の向上 |
| Microsoft Defender | スキャン頻度とタイミング調整 | 使用中の負荷軽減 |
| イベントビューアー | 遅延アプリの特定・整理 | ボトルネック排除 |
25H2アップデートのメリットも忘れずに
「重い」という声がある一方で、25H2には目立たないながらも実用的な改善が数多く含まれています。
ここでは、セキュリティ・安定性・保守性の観点から見る25H2のメリットを整理します。
セキュリティ修正と保守性の向上
25H2は、2025年10月に発生した回復環境(WinRE)のUSB入力不能問題を修正するKB5070773を含む更新です。
加えて、古い管理ツール(PowerShell 2.0やWMIC)の削除など、システムの保守性を高める調整も行われています。
“目に見えない安心”が25H2の大きな価値といえるでしょう。
| 改善項目 | 概要 | メリット |
|---|---|---|
| WinRE修正(KB5070773) | USB入力問題を解消 | 回復環境の信頼性向上 |
| 古いコンポーネント削除 | PowerShell 2.0、WMICなど | 保守性アップ |
| Defender強化 | スキャン安定化、誤検知削減 | 安全性と快適性の両立 |
安定性と軽量化を両立した設計の意義
25H2では、新機能の追加を控えた代わりに、システム最適化と軽量化が進んでいます。
特にバックグラウンド動作の効率化やプロセス管理の改善により、リソースの消費が安定しています。
これにより、企業利用やクリエイティブ作業など、長時間稼働を求めるユーザーにとっても恩恵が大きいバージョンです。
「重くないWindows」を維持する設計思想こそが、25H2の真の価値といえるでしょう。
| 側面 | 改善点 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| システム軽量化 | バックグラウンド最適化 | 負荷の平準化 |
| 安定性 | 更新方式の簡略化 | トラブル発生率の低下 |
| 保守性 | 不要コンポーネント削除 | 長期運用の信頼性向上 |
まとめ:一時的な重さは“収束する”過程
Windows 11の25H2アップデートで「重い」と感じても、それは一過性の現象であることがほとんどです。
更新直後のバックグラウンド処理やドライバ再最適化が完了すれば、性能は24H2と同等、もしくはそれ以上に安定します。
最後に、この記事全体の要点をまとめておきましょう。
恒常的な低速化の可能性は低い
25H2は有効化パッケージ方式で提供されており、OSコアや構造が大きく変わるわけではありません。
そのため、アップデート自体が根本的な性能低下を引き起こすことは考えにくいです。
「重さ」は一時的なインデックス再構築やスキャン負荷に起因するケースが大半です。
数回の再起動と放置で自然に解消する場合が多いため、まずは時間を置いて様子を見るのが最善です。
| 原因 | 発生タイミング | 解決の目安 |
|---|---|---|
| 検索インデックス再構築 | 更新直後 | 1〜2時間 |
| Defenderスキャン | 定義更新後 | 数時間 |
| OneDrive再同期 | 初回ログイン時 | 完了後に収束 |
測って直す姿勢が、快適なWindows運用のカギ
体感的な印象だけではなく、イベントビューアーや信頼性モニターなどのツールを使って実際の数値を確認することが大切です。
もし特定のアプリやドライバが遅延の原因であれば、アップデートや削除、再インストールなど具体的な対策を講じることができます。
「感覚」ではなく「データ」で判断することで、無駄な設定変更を避け、的確に改善できます。
“重くなった”を放置せず、原因を測定して対処することが、安定したWindows運用の第一歩です。
| 確認手段 | 得られる情報 | 改善に役立つポイント |
|---|---|---|
| イベントビューアー | 起動時間・遅延プロセス | ボトルネック特定 |
| 信頼性モニター | エラー発生履歴 | 不安定なアプリの特定 |
| WPR/WPA | CPU・I/Oトレース | 根本原因の可視化 |
もし上記を行っても改善しない場合は、クリーンブートや修復インストールを検討してみてください。
また、Microsoft公式の既知の問題ダッシュボードを定期的にチェックし、最新の修正を適用する習慣を持つことも有効です。
アップデートは「悪」ではなく、安定した環境を維持するための“メンテナンス”として前向きに付き合うのがポイントです。